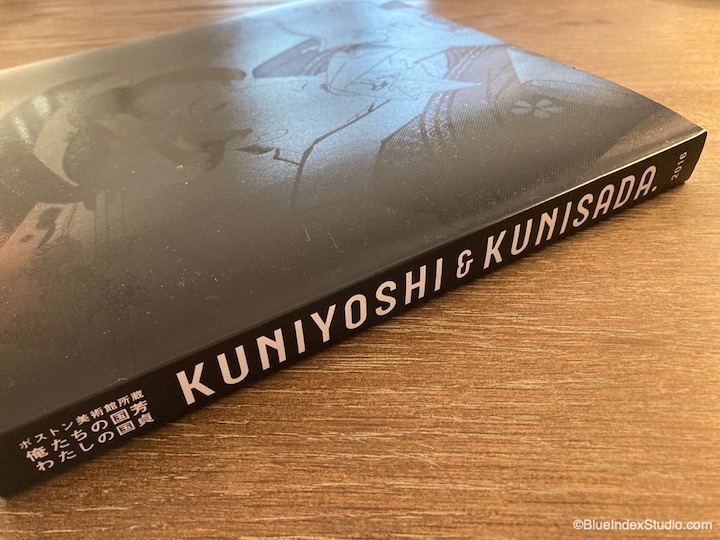黄金様式で知られるグスタフ・クリムトは19世紀末から20世紀初頭オーストリアを代表する画家だ。1897年には古典主義からの脱却を望む芸術家を率いてウィーン分離派(Wiener Secession)を立ち上げた。ウィーン芸術の近代化を目指しヨーロッパ各地で起こった美術と工芸の融合(Arts and Crafts Movement)をウィーンで率いたのはクリムトだった。
ヨーロッパではこの頃「ジャポニスム」といわれる日本趣味・日本美術ブーム。
浮世絵版画の認知は、海外最初の記録はフランスのF. ブラックモンと《北斎漫画》との出会いが始まりと言われている。年代については1856年、1859年など諸説ある。それより前の1851年には最初の国際博覧会がロンドンで開催されたが、日本最初の参加(ごく小規模)は1865年のパリ万博まで待たなければならなかった。そして日本政府としての正式参加は1873年のウィーン万博となった。浮世絵は当時の展示品リストに含まれている(西川, 2007)。この時日本パビリオンは大変な盛況で、ウィーン中が「扇」だらけになったという記録もある(西川, 2007)。こうした経緯から日本文化はクリムトの活動期には芸術家知識人などのあいだですでにある程度認知されていたと考えられる。
クリムトは1862年生まれ。1876年にはウィーン工芸学校で学んだ。父親は金細工師。後のウィーン近代化に向けた力強い活動からも、美術・工芸分野の世界的な動向を注視していたことがうかがえる。そして多くの芸術家同様に浮世絵版画を収集していた(Herring, 2022)。

Wien Museum
Inventory number 45677
左は長年クリムトのパートナーであったファッションデザイナーのエミリア・フレーゲの肖像。平面的で意匠化された画面・配色などにジャポニスムの影響が見られる。
画面の右下に黄色と緑の正方形。
黄色の正方形は名前と姓が改行して書かれています。左右がきっちり合っていて、その下に一行分の空白を取り、最後に作品年を左右に二文字づつ分けて、中心に二文字分ほどの空白をとっている。
緑の正方形は、GとKでデザインされたモノグラム。ウィーン分離派のメンバーは全てモノグラムを持っており、現在のThe Vienna Secession公式サイト*でも見ることができる。
名・姓・作品年を改行しデザインされた署名には、同時期のもう一つの潮流アール・ヌーヴォーの特徴も見える。
しなやかな曲線・曲面と装飾で描かれる画面では文字デザインも入念に行われ、こうしたスタイルの署名は同時期のほかの作家作品でもたびたび見られる。しかしその多くは背景に溶け込むように、いわばあまり目立たない署名が一般的だ。
しかしクリムトの場合、その部分の地色を変えて背景から際立たせている。作品内に使われている二色を用いたとはいえ、黄色の地に黒の署名は特に引き立っていて、フレーゲのデコルテに描かれた幾何学模様以上に目を引く。

歌川広重 国立国会図書館
こちらは広重の《名所江戸百景 深川木場》。浮世絵版画では画題や絵師名などを様々な形に枠取りし、彩色をして際立たせる方法は頻繁に使われる。名所江戸百景シリーズでは、署名とシリーズ名は短冊型、サブテーマが正方形で、右上に2つ並べた赤と黄のタイトルは黒色のはいけいから一層引き立っている。
クリムトを語るとき、琳派との関連を取り上げられることが多い。このフレーゲ肖像の青・緑・黄の色使いにも琳派の雰囲気を感じる。落款風の署名は、肉筆書画の観察によるだろう。そしてクリムトも浮世絵を仕事場の壁にかけていた(Herring, 2022)ということも知られている。
クリムトが《名所江戸百景》を実際に見たかどうかはわからない。この名所画がクリムトのコレクションになかったとしても、浮世絵をはじめとする日本美術からのインスパイアを受けたことは想像に難くない。
クリムトにとってのジャポニスムは、さまざまな時代の潮流と相まった独自のスタイルを生み出すほどに昇華された。そのことがよく伺える肖像画だと思う。
参考文献
《Bildnis Emilie Flöge》Wien Museum
https://sammlung.wienmuseum.at/en/object/820521-bildnis-emilie-floege/
西川智之 2007「ウィーンのジャポニスム 1873年ウィーン万国博覧会」『言語文化論集 』27 (2) 名古屋大学大学院国際言語文化研究科
歌川広重《名所江戸百景 深川木場》国立国会図書館(NDL)デジタルコレクション(2022/10/03閲覧)
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1312342?tocOpened=1
博覧会 近代技術の展示場(2022/10/03閲覧)
https://www.ndl.go.jp/exposition/s1/index.html
Sarah Herring 2022 「Why do artists sign their works of art?」National Gallery London
https://www.youtube.com/watch?v=PQqSjrz29eU
*The Vienna Secession公式サイト(2022/10/03閲覧)
(クリムトのこの作品のモノグラムは現在サイトで見られるデザインとは異なっている。)https://www.theviennasecession.com/monograms/