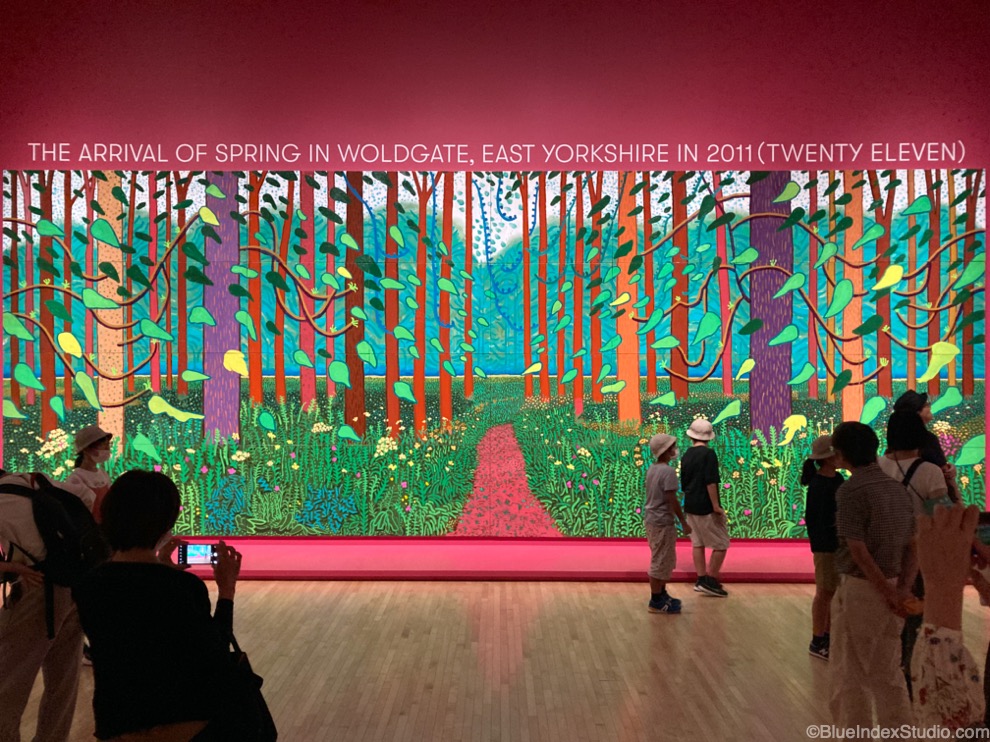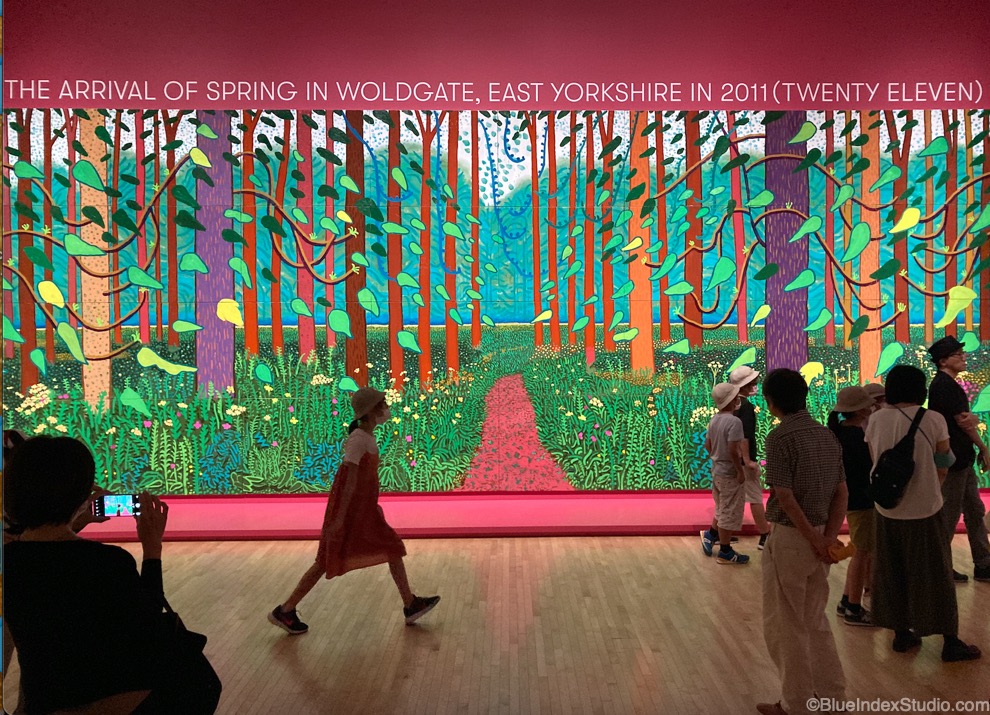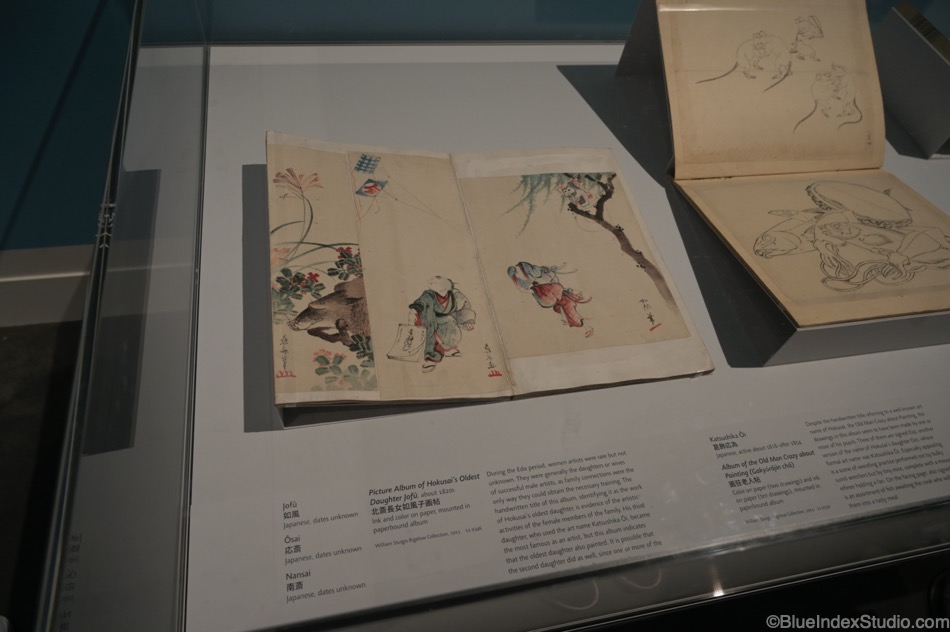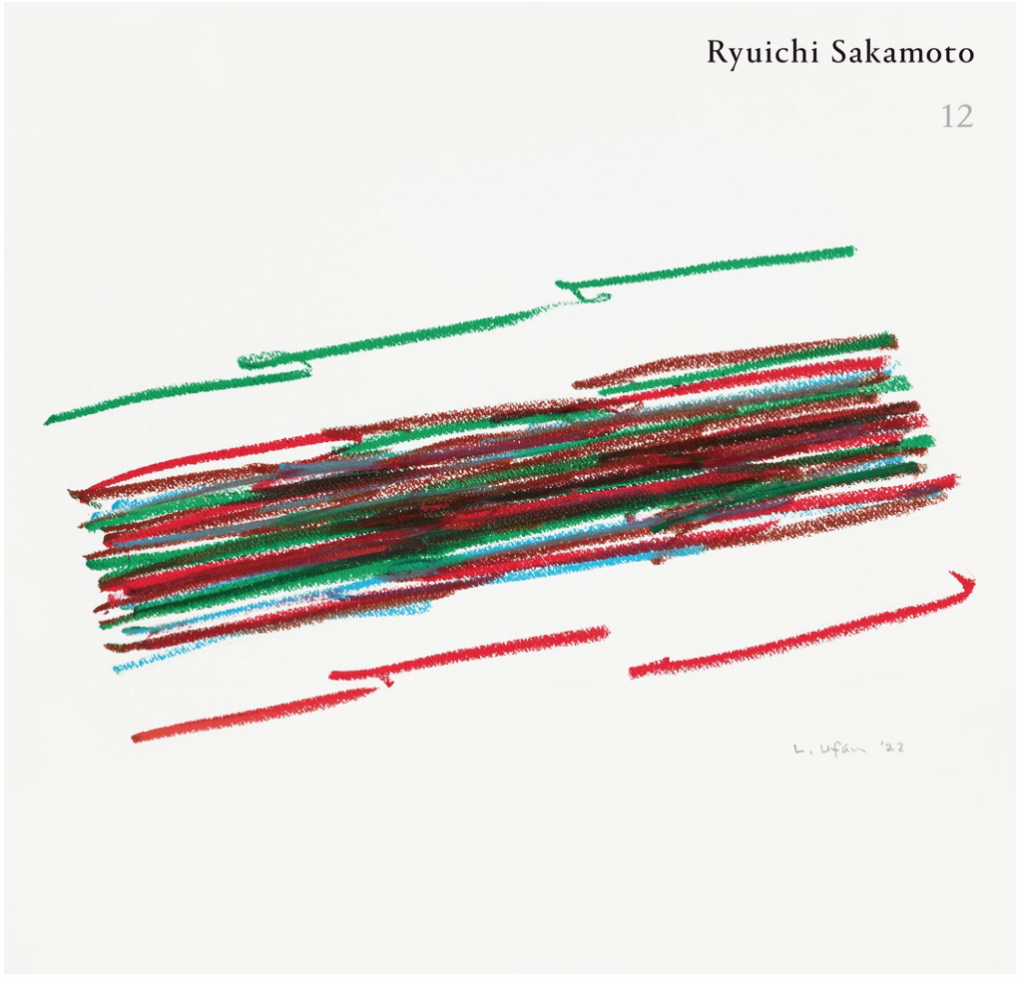世界には数え切れないほど美術館があるが、美術史を詳細に辿ることが出来るコレクションを持つ美術館は多くはない。その中でも自分が訪ねることができる美術館となるとほんの僅かだ。そのわずかな美術館であっても館内すべての展示を鑑賞できた美術館は皆無であり、足を止めた作品すべてが鮮明に記憶に残っているわけではないことは甚だ不本意なばかりだ。アート好きとしては情けなくなるが、これが現実なのだ。ということは、足を止め、鑑賞して記憶に残っているという作品とは唯ならぬ縁があるに違いないと私は捉えている。
この作品もそういった縁を感じる作品たちの中の一作と言える。
ロヒール・ファン・デル・ウェイデン(Rogier van der Weyden, 1400 – 1464)。ロベルト・カンピン、ヤン・ファン・エイクとともに初期フランドル・北方ルネッサンス絵画の三大巨匠の一人である。ボストン美術館は『聖母を描く聖ルカ』を所蔵している。当館はこの作品をアメリカ合衆国における北方ヨーロッパ絵画の最重要作品と位置づけている。

(about 1435–40) MFA: 93.153
向かって左に聖母子。天井から二人の背後まで背面はオリーブ色、表面は金糸と赤で織られ縁取りで整えられたタペストリー。その前でゆったりと腰を下ろす聖母マリアの衣装は彼女の色とされるブルーを中心に金色がアクセントがいろいろな方法で取り入れられている。マントの控えめな縁取りもそうだが、袖に施された立体感のある刺繍も布の質感の豪華さも非常に詳細だ。そしてこの母と子の日常の営みにはそこはかとない穏やかな優美さが表現されている。こうした聖母子をペンと紙を手にしながら見つめる聖ルカ。真剣な表情には緊張が隠せない。ただ聖母子を見る眼差しは、感動と喜びでほとんど恍惚として見える。
微細にわたって美しく描かれた室内は二本の柱を境に神聖な場面が区切られて、市井の世界へと外に開かれていく。中心の水辺は左右に緩やかな入江を作りながら中心を維持し、鑑賞者の視線を遥か遠くまで導いている。そして外には人々の日常の暮らしが見える。
伝えるところによると、聖ルカは最初に聖母子の肖像を描いたと伝えられている。そのために聖ルカは芸術家の守護聖人となった。聖母子を描く聖ルカは中世絵画には度々見られる。
ロヒール・ファン・デル・ウェイデンはニューヨークメトロポリタン美術館所蔵の三連祭壇画『メロードの祭壇画』を描いたと言われるロベルト・カンピンに師事したといわれる。師弟共同制作と考えられる作品も多く「どちらの仕事か?」研究は今も続いている。両者の作品を比較すると師匠カンピンの方が彫り込んでいるような立体感が見え硬い印象を受ける。一方、ロヒールの方は、より絵画的な立体感なために優しい穏やかな印象を残す気がする。
しかし、ロヒールは署名(記名)作品を残していないそうだ。つまり基準作品がそもそもないということになる。MFAはこの『聖母を描く聖ルカ』のX線検査を行い、聖ルカの慎重な容貌の表現に、聖ルカはロヒールの自画像の可能性があるとしている。これが本当だとしたら、ロヒールは聖母子を描く聖ルカになり変わっている自らに心がふるえ、湧き上がる感動を押されるような表情になったのかもしれない。
<参考サイト>
Rogier van der Weyden 《Saint Luke Drawing the Virgin》(about 1435–40)
https://collections.mfa.org/objects/31035/saint-luke-drawing-the-virgin?ctx=49616447-e018-48d1-884d-c48f36bb6105&idx=0